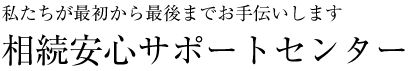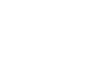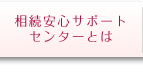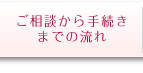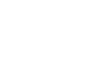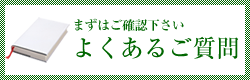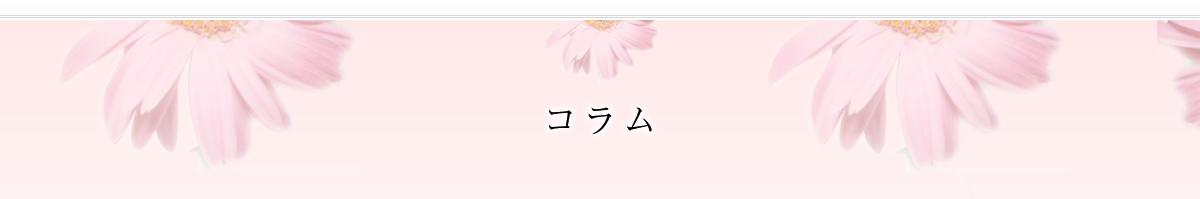
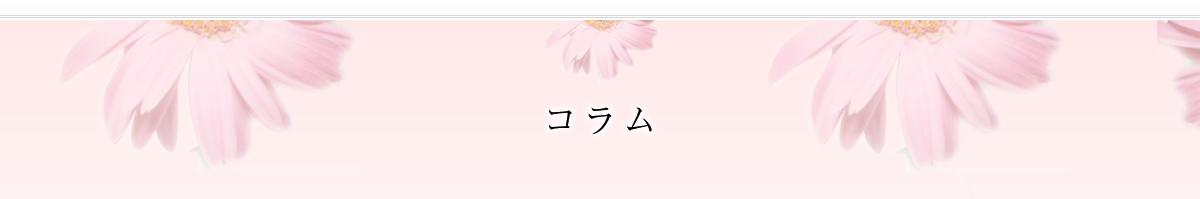
コラム
遺言の必要性
文具メーカーから発売され、年間2万冊も売れているという「エンディングノート」。
2009年に発売された高齢者向けの「遺言書キット」が好評で、今度は若い世代に必要な情報も記録できるツールとして、<もしもの時に役立つノート>という商品が開発されたそうです。
今日は、相続、遺言書の実情についてお話ししたいと思います。
日本は、総人口に占める65歳以上の高齢者の割合が23%を超え、さらに75歳以上の高齢者の割合が10%を超える、超高齢社会になっています。
その中で、次世代への資産の承継、「相続問題」がますますクローズアップされつつあります。
増加する相続問題と遺言
相続財産をめぐる争いは、テレビドラマなどでたびたび取り上げられるくらい増加傾向にあります。
家庭裁判所が取り扱う遺産分割事件が1972年には年間約4900件であったのに、2010年度は約1万849件に達し、2倍余りに増えています。
そして、その傾向に歩調を合わせるかのように、公証役場で遺言をする事例も多くなっています。
このように親族間で相続財産をめぐるもめ事が起こり易くなり、遺言も増えているということは、遺言をしておかないと、法律で定められたすべての相続人から遺産についての権利の主張が行われがちで、相続をめぐる争いがしばしば起こるようになったことが挙げられます。
戦前、日本では家督相続制度が採られ、多くは長男が全財産を1人で相続する建前でしたから、相続争いも少なく、遺言をする人はほとんどいませんでした。
戦後は、法の下の平等の理念から共同相続制度が採用されましたので、遺言がないと、共同相続人が必ず遺産分割協議をしなければならず、その協議がまとまらなければ、家庭裁判所の調停または審判で決めることになります。
相続人間の争いは、この遺産分割協議のときに表面化してくるのです。
被相続人が財産を残して死亡した場合、それぞれの相続人にとっては、その遺産分割協議の時こそが財産を取得する機会となります。場合によっては、何億、何千万円という財産が手に入るというケースもあります。相続人は遺産分割の機会を利用して、自分のために少しでも多くの財産を得たいと思い、各自が自己の権利を主張し合うことが多いのです。
被相続人としては、せっかく残した財産ですから、子孫が仲良く分け合い互いに助け合って暮らすことを願っていると思いますが、その気持ちとは裏腹に、その財産がかえって争いのもとになることもあるのです。
そこで、自分の死後、遺産をめぐり子供たちや親族間に起こる争いを未然に防ぐために、遺言をして、あらかじめ各相続人の取り分や分配の方法を具体的に決めておくのがよいのです。これが、遺言を必要とする一つの理由で、実際にそのようなことを考えて遺言をする人が増えてきています。
一般的に、遺言が必要な場合としてはこのような例があります。
(1)夫婦の間に子供がいない場合
遺言がなければ、相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合、妻の相続分は4分の3で、残りの4分の1は夫の兄弟姉妹が相続することになります。
(2)息子の妻に財産を贈りたい場合
息子の妻は、夫の両親の遺産については、全く相続権がありません。例えば、夫に先立たれた妻が、亡夫の親の面倒をどんなに長い間みていたとしても、亡夫との間に子供がないときは、亡夫の親の遺産は、すべて亡夫の兄弟姉妹が相続してしまいます。
(3)特定の相続人に事業承継、農業承継をさせたい場合
例えば、その子が親の片腕となって事業の経営に当たっている場合には、その事業用財産や株式が法定相続により分割されると、経営の継続が保てなくなることがあります。
(4)内縁の妻の場合
内縁の妻には、夫の遺産についての相続権は全くありません。したがって、内縁の夫が内縁の妻に財産を残したいのであれば、遺言で遺産を贈る配慮をしておくことが必要です。
(5)相続人が全くいない場合
相続人がいない場合は、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。遺産を親しい人やお世話になった人にあげたいとか、社会福祉関係の団体・教会等に寄付したいという場合には、その旨を遺言しておく必要があります。
(6)その他
相続人間で紛争が予測される場合、知人や友人に遺産を贈りたい場合、相続権のない孫に遺産を贈りたい場合、障害者である子供により多くの財産を残したい場合などは、あらかじめ遺言で、相続人間の遺産の分配方法や相続人以外に特定の人や団体に遺産を贈ることなどをはっきりと決めておくことが必要です。
平成24年6月22日
司法書士 尹 炳泰